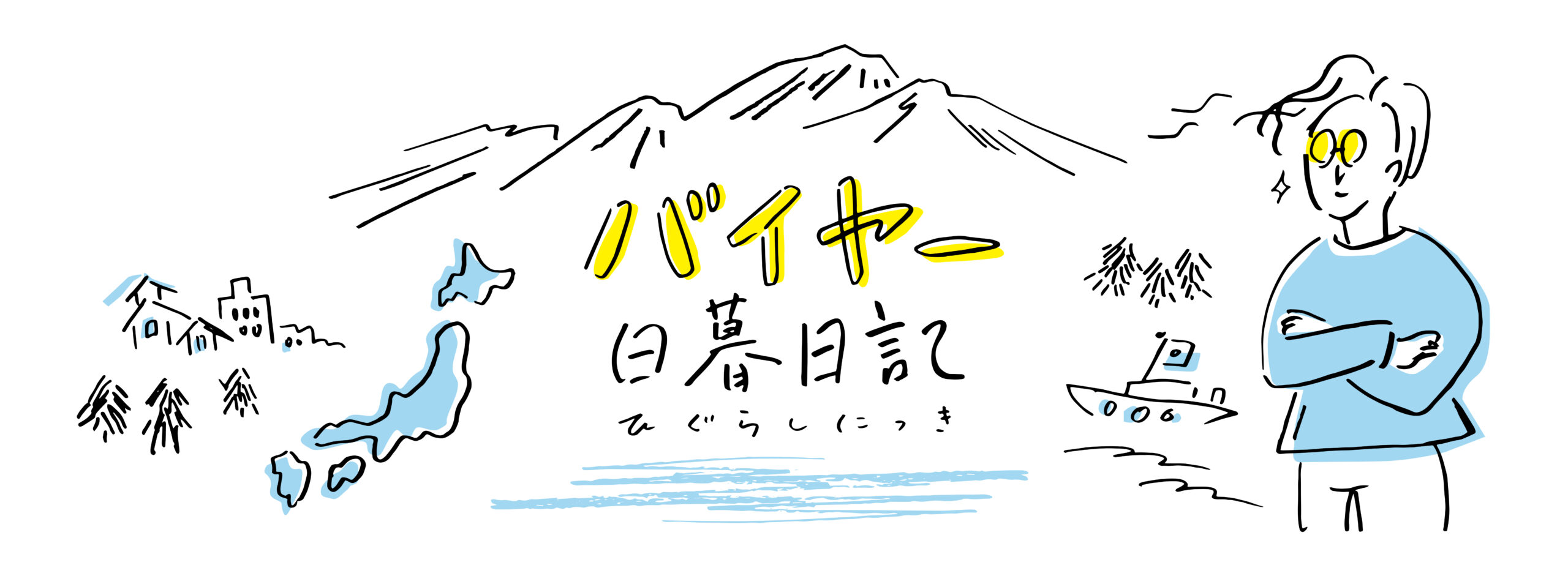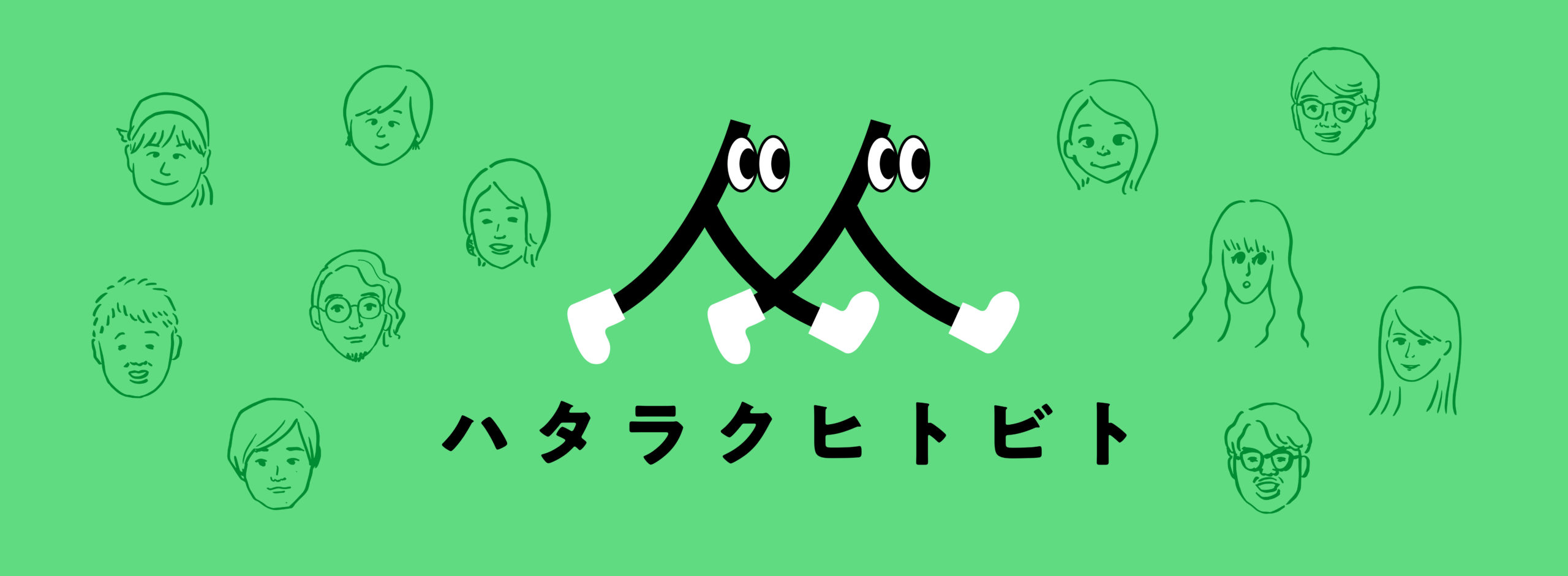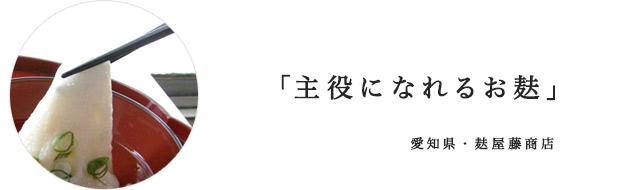
東京から新幹線で約2時間。
岡崎城やオカザえもんで有名な愛知県岡崎市で、代々“手作り”にこだわり続けるお麩屋がある。
大正14年創業の老舗【麸屋藤商店(ふやとうしょうてん)】だ。

左から、3代目当主の柵木(ませぎ)卓三さん、4代目の隆宏さん、奥様の加奈子さん、3代目の奥様 美恵子さん。
その他4名の女性従業員の皆さんで、手作りにこだわったお麸を作り続けている。
※写真には写っていないが、86才の2代目も現役で活躍中。
規則的な機械音と芳ばしい香りが漂う工場で、3代目の卓三さんにお話を伺った。

お麸作りは朝5時から始まる。
温度に敏感なグルテンの具合で加水の量を調整するため、気温の落ち着いている早朝に生地を仕込みはじめるのだ。
この日焼き場に立っていたのは、4代目の隆宏さん。
黙々と焼き麸を作る姿は、まさに職人といった雰囲気。

ここでは昔ながらの【製麸用電熱器】を使って焼き麸を製造している。
隆宏さんによれば、特に温度調節と打ち水の量に気をつけているとの事。
オートメーションが主流となる中で時代の流れに反しているかもしれないが、手作りにこだわる麸屋藤商店には無くてはならない機械だ。
日本の伝統食品であるお麸だが、製造には技術と体力を必要とする。
昔はたくさんあったお麸屋も徐々に減っていったという。

隆宏さんの奥様、加奈子さんが麸屋藤商店へ嫁いできたのは10年前。
それまでお麸に馴染みがなく、実はお麸自体がおいしいと思ったことがなかったという。
しかしいざ料理に使ってみると、お麸を使うことによって断然おいしくなったり、「たま麸」に限っては今まで麸はお吸い物のおまけ…といった概念を覆らせる、まさに主役になれる商品だと思った。

『自分が味わったこの感覚を全国の皆様に知って頂きたい』
毎日お麸の話ばかりしているという4代目夫婦。
最近は「お餅の代わりに」と介護センターから注文があったり、たま麸をお子様と毎日食べているいうお客様の声も頂いている。
『食べて頂ける皆様により良いものを提供できるよう、従業員一同精一杯製造していきたい』と今後の意気込みを語ってくれた。
今回の工場見学では、代々受け継がれる作り手の技術と熱い想いを伺う事ができた。
手作りにこだわる麸屋藤商店だからできる、新しいお麸のカタチ。
食べればきっとその魅力を感じられるはずだ。

※こちらは2016年に作成した記事になります。掲載当初大変好評だったため、今回再掲載させていただきます。過去の記事になりますので、当時と現在とで実際の内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。
今回のヒャッカ

全国各地の作り手さんと、作るモノ、そしてそのこだわりに迫る企画。日本百貨店が出会った、日本のモノヅクリの技術と精神、その裏にあるヒトの心とは。
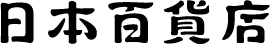
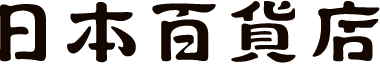
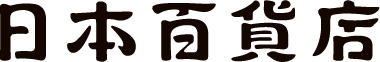
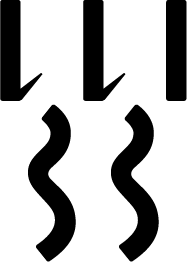


 服飾雑貨
服飾雑貨